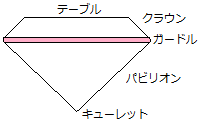|
| 図1、300mmの長光路セルと大型試料室 |
分光光度計の測定光はレーザーではないため、光路長が長くなると光束が広がってしまいます。光束の広がりによる測定値への影響を抑えるため、検出器部に積分球を採用しました。この装置で測定した吸収スペクトルから、色度座標xyと明度Y*を算出します。
図2は、浄水、水道水、地下水、河川水の測定データです。光路長10mmのセルで測定した場合は、色度座標xy及び明度Yから色の違いを識別することができませんでしたが、300mmのセルではその違いをハッキリと識別できました。
このように、吸光度が極めて小さい水のような試料を測定するには、光路長を長くすることが有効です。
 |
| 図2、10 mm(上)、300 mmセル(下)の 色度座標xyと3刺激値Y |